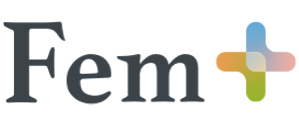女性のロールモデルが働きやすさ改善のポイント。
育成方法や事例を紹介
女性の活躍推進を本格化させたい企業にとって、女性の「ロールモデル」の存在は非常に重要です。
本記事では、ロールモデルの定義や導入方法、実際の企業事例までを分かりやすく紹介します。
社内のキャリア形成やモチベーション向上に課題を抱える人事・総務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
 ロールモデルとは?
ロールモデルとは?
ロールモデルとは、他者にとって模範となる人物のことです。企業や労働に関する場面で使われるときには、周囲の人がその人の行動や考え方に感銘を受け、「自分もこうなりたい」「こんな働き方がしたい」と思わせるような存在を表します。ダイバーシティの推進が加速している現在の日本の労働環境においては、従来の働き方にとらわれない、多様で柔軟な働き方を実現する人がロールモデルとして注目される傾向が強くなっています。たとえば下記のような人がその一例です。
- ワークライフバランスを保ちながら成果を出す人
- 時短勤務やリモートワークを活用してキャリアを築く人
- 育児や介護と両立しながら管理職を務める人
- 性別や年齢に関係なく、リスキリングなどによって新しいキャリアの道を自身で切り開く人
ただし、ロールモデルというのは労働環境以外でも存在します。従って、ロールモデルは必ずしも育児や介護をしながら働く女性とは限りません。また、ロールモデルは必ずしも同性であったり、管理職であったりする必要はありません。しかし、多くの人に影響を与えやすい人となると、公私ともに一定の成果を上げているケースが多いといえます。特に女性のキャリア形成においては、同じ立場や背景を持つ先輩社員の姿が、将来像をイメージする手助けとなります。個々の従業員がロールモデルから具体的な行動や考え方を学ぶことで、従業員の自律的なキャリア開発が進みやすくなります。
 女性の活躍推進におけるロールモデルの重要性
女性の活躍推進におけるロールモデルの重要性
女性が自身のキャリアを描くうえで、「身近に目標となる人物がいる」ことは大きな支えになります。女性の社会進出は大幅に進みましたが、一方で、育児や介護など家庭での負担はまだまだ女性に偏りがちです。ライフステージが変わる際に、プライベートとキャリアの両立に悩む女性は少なくありません。また、女性が働きやすい環境を整え切れていない企業も多く、社内の制度や従業員の意識が女性のキャリアの足かせになってしまうケースもあるでしょう。こういった背景から、特に女性が管理職や専門職への登用を目指す際、実際にそのポジションで活躍している女性がいれば、「自分にもできる」と感じやすくなるのです。これにより、社内の女性人材の定着率や挑戦意欲が高まります。
 企業が女性のロールモデルを設定するメリット
企業が女性のロールモデルを設定するメリット
では、女性のロールモデルを設定するその他の具体的なメリットを考えてみましょう。
キャリア形成の指針になる
女性社員にとって、社内に自身と同じような背景やライフイベントを経験しながら活躍しているロールモデルの存在は、将来像を描く上での大きな手がかりとなります。例えば、出産・育児・介護といったライフステージを経ながらもキャリアを継続している先輩社員の姿は、「自分にもできる」という具体的なビジョンを与えてくれます。ロールモデルを通じて、必要なスキルや経験、価値観を学ぶことで、女性社員自身が自信を持ってキャリア設計に取り組むことができ、主体的に成長を目指す意識が醸成されます。
モチベーションの向上につながる
ロールモデルの存在は自分自身の将来を前向きに捉えるための重要な要素です。たとえば出産・育児・介護といったライフイベントを乗り越えながらも、組織の中で活躍を続ける女性の姿は、「私にもできるかもしれない」という希望や勇気を与えてくれます。また、同じような悩みや壁を経験してきた先輩女性のリアルな声や体験談は、自分の課題の解決を得るヒントになります。こうしたロールモデルとの接点を持つことで、女性社員のキャリア意欲や自信が高まり、組織全体のエンゲージメントや活気の向上にもつながります。
多様な人材が活躍できる風土が育まれる
さまざまな立場やライフステージにあるロールモデルが社内に存在することは、「自分らしく働ける職場」と実感する大きな要因になります。たとえば、子育て中のマネージャーや、キャリアを一時中断し復職したベテラン女性社員など、多様な働き方を体現するロールモデルがいれば、それぞれのライフスタイルに合ったキャリア形成への希望が持てます。こうした環境は、女性社員が安心して挑戦し、長期的に活躍できる風土の醸成に貢献します。さらに、今では育児や介護に関わるのが女性だけとも限らず、性別・年齢を問わずライフスタイルが多様化しています。企業全体としても「多様な価値観や人生設計を尊重する文化」が根付き、男女問わず柔軟な人材活用や組織力の強化につながります。
離職率の低下につながる
女性社員がキャリア継続に対して感じる不安の多くは、出産・育児・介護など、ライフイベントとの両立にあります。実際、内閣府の調査でも、第一子出産前後に退職した女性は23.6%であり、また、介護や看護を理由とした離職者は女性が8割近くを占めることがわかっています。そうした課題を乗り越えて活躍している女性ロールモデルの存在は、安心して働き続けられる環境が整っているという証になり、離職への心理的ハードルを大きく下げることができます。また、ロールモデルが具体的にどのように制度を活用し、上司や同僚と連携しながら仕事を継続しているかを見せることで、キャリア形成の現実的なイメージが持てます。女性社員にとって「この会社で働き続けたい」と思える環境づくりの鍵となり、結果として離職率の低下や優秀な女性人材の定着につながります。
 女性の活躍推進のためのロールモデルの導入と普及
女性の活躍推進のためのロールモデルの導入と普及
ロールモデルの導入は、女性のキャリア形成を後押しするために欠かせません。ここでは、導入から育成・発信・評価までの具体的な方法をご紹介します。
ロールモデルを設定する
まずは社内において、一定の実績を持つ女性社員をロールモデルとして明確に設定しましょう。女性ならではの課題やライフイベントを乗り越えてキャリアを積んできた人材を選出することで、他の女性社員にとって現実的な目標像となります。役職や部署にとらわれず、育児との両立を実現している社員、キャリアチェンジを成功させた社員、時短勤務でも成果を上げている社員など、さまざまなロールモデルを複数提示することが理想です。多様な女性の生き方や働き方を可視化することで、社員一人ひとりのキャリア意欲を引き出すことができます。
ロールモデルとして活躍できる人材を育成する
特に女性管理職が少ない職場などでは、企業側がロールモデルを意図的に育成していく必要があります。女性社員の場合、ライフイベントや性別による無意識のバイアスを乗り越えるサポートに力を入れましょう。マネジメント研修やキャリア支援制度、メンター制度の整備に加えて、社外の女性リーダー向けセミナーや異業種交流会、ダイバーシティをテーマにした外部講座への参加機会を提供することも有効です。外部の視点や他社の女性ロールモデルに触れることで、自身のキャリアに対する視野が広がり、自信やモチベーションの向上につながります。また、育成過程を社内で可視化することで、若手女性社員のキャリア形成の参考にもなります。育成はスキルの習得にとどまらず、多様な価値観や人生観を尊重しながら、長期的な視点で支援することが重要です。
ロールモデルの存在を社内外に広める
ロールモデルの存在を広く伝えることは、女性社員のキャリア意識を高め、組織全体にポジティブな影響を与えるうえで非常に効果的です。社内報やイントラネット、SNSなどの社外広報ツールを活用し、ロールモデルの働き方や価値観、キャリアパスを積極的に発信しましょう。特に女性社員へのインタビューやライフイベントとの両立エピソード、成功までのストーリーなどは共感を呼び、女性社員自身のキャリア形成に希望を与えます。また、外部への情報発信は企業のダイバーシティ推進の姿勢を明確に示すことにもつながり、採用活動や企業ブランディングにも好影響をもたらします。
効果・成果を測定する
ロールモデル施策を導入した後は、継続的な効果検証と改善が不可欠です。女性管理職比率や女性社員の昇進スピード、育児休業からの復職率、時短勤務者の定着率など、女性特有の課題に着目したKPIを設定することが重要です。また、定期的な社内アンケートやヒアリングを通じて、ロールモデル制度に対する女性社員の満足度や信頼度を確認しましょう。ロールモデル本人へのフィードバックや成果の可視化も行い、社内の成功事例として共有することが、さらなる改善と社員の納得感につながります。
 企業の女性のロールモデル施策の成功事例
企業の女性のロールモデル施策の成功事例
実際にロールモデルを活用して成果を上げている企業の取り組みを知ることは、自社での施策検討における参考になります。ここでは、女性リーダー育成に力を入れる企業の成功事例をご紹介します。
大塚製薬株式会社:女性リーダーを育成する活躍の場づくり
大塚製薬株式会社は、1980年代というダイバーシティの概念がまだ広く認知されていなかった時代から、年齢・性別・新卒・中途・国籍にとらわれない多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進してきました。特に女性医薬情報担当者(MR)の積極採用を行い、キャリア形成の機会を平等に提供することに尽力しています。さらに、女性リーダーを対象とした独自の育成プログラムを実施するほか、年1回の管理職研修によってマネジメント層の意識改革も図っています。本人の希望に応じた多様なキャリアパスが整備されており、働く女性一人ひとりの可能性を引き出す取り組みが行われています。
東京急行電鉄株式会社:女性社員や管理職対象の研修を実施
東京急行電鉄株式会社では、顧客マーケティング力の向上と質の高い労働力の確保のため、ダイバーシティマネジメントの推進の必要性を強く感じ、女性活躍を含めた多様性推進に本格的に取り組んでいます。特に「制度」「風土」「マインド」の3つの観点から施策を展開しており、女性管理職の少なさという課題に対し、2014年から積極的に女性社員向けの社内研修や外部派遣などを実施しています。また、女性社員がロールモデルを見つけやすい環境づくりを目指し、グループ会社の女性管理職を集めたフォーラムを開催。そこには上司や各社人事担当役員も参加し、組織全体で女性のキャリア支援を進めています。さらに、女性管理職と若手女性社員との座談会も行い、世代を超えた交流とキャリアの展望形成を後押ししています。
株式会社ノバレーゼ:「キラキラ働こう!プロジェクト」の実施
結婚式場の運営を中心とする株式会社ノバレーゼでは、土日祝日や夜間など、現場業務の特性上ワークライフバランスの確保が難しいという課題がありました。従来は配置転換などで復職後の女性社員に対応していましたが、それだけでは今後すべての社員に対応するのが難しいとの課題意識から、2014年に「キラキラ働こう!プロジェクト」をスタートしました。このプロジェクトでは、土日祝日であっても、子どもの運動会や冠婚葬祭などでの休暇取得を明確に認めるルールを整備し、繁忙期でも休みやすい仕組みを導入。社員一人ひとりがライフイベントと両立しながらも、自分らしく働き続けられる環境整備を進めています。この取り組みを通じて、社内ロールモデルの可視化と、それに対する上司・同僚の理解促進にもつながっています。
 女性のロールモデルは女性活躍のために欠かせない存在
女性のロールモデルは女性活躍のために欠かせない存在
ロールモデルの導入は、女性社員が将来のキャリアを描くための大きな後押しとなります。ロールモデルの設定・育成・広報・効果と測定の4ステップを通じて、継続的な推進が求められます。まずは自社で活躍している女性社員の見える化から始めてみましょう。多様な人材が輝く職場づくりの第一歩となるはずです。
【監修】
佐野 真子
キャリアコンサルティング総研株式会社代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
企業のセルフキャリアドック導入及び3000名以上の従業員面談、両立支援に携わる。厚生労働省が進めるキャリア形成・リスキリング事業や就職ガイダンス事業に携わり、キャリアデザインセミナーや面談を実施。キャリコンバンク®事業では、企業顧問及び社外相談窓口を通じて、AI時代の働き方についても企業の事業創造とキャリア形成を支援している。
著書
「現代版キャリア革命:昭和世代のための頑張りすぎない生き方を手に入れる方法」
「ビジネスパーソンのための色彩心理活用術 キャリアカラーセラピー®」