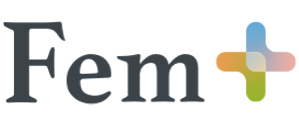妊活では何をするの?
妊娠しやすいタイミングや妊活中に気をつけたい
行動について解説
妊活では何をするの?
妊娠しやすいタイミングや妊活中に気をつけたい行動について解説
妊活とは、妊娠を希望する男女が妊娠に向けておこなう活動全般のことです。妊活を成功させるには、生活習慣を整えたり体を冷やさないようにしたりなど、妊娠に向けた体づくりからおこなう必要があります。
そこで本記事では、妊活でやるべきことや妊娠しやすいタイミング、妊活中に気を付けたいことについて解説します。
 妊活とは妊娠するための準備や行動のこと
妊活とは妊娠するための準備や行動のこと
妊活とは、妊娠を望む男女が妊娠に向けておこなう準備や行動全般のことです。
明確な定義はありませんが、具体的には下記のような行動が挙げられます。
● 妊娠に向けて夫婦で話し合う
● 妊娠について正しく理解する
● 妊娠しやすい体を作るために生活習慣や食生活を改善する
● 夫婦で婦人科を検診する
● 妊娠しやすいタイミングで性交渉をする
● 必要であれば不妊治療をおこなう
妊娠するには夫婦で協力する必要があるため、妊活は女性だけではなく男性も積極的に参加するのが望まれます。
自然妊娠は簡単ではないからこそ妊活が必要
「避妊しなければすぐに授かれるはず」「まだ若いからすぐに妊娠できる」というように、妊娠は自然にできるものだと思っている方も多いのではないでしょうか。
実は、夫婦が望んで自然に妊娠する確率は意外と低く、そう簡単に授かれるものではありません。
妊娠しやすい20代の健康的な男女が避妊せず性交渉した場合でも、自然妊娠に至る確率は25~30%程度だとされています。
参考:M.Sara Rosenthal.The Fertility Sourcebook.Third Edition
30歳以降になると妊娠率が徐々に低下し、35歳以降になるとその傾向が顕著に現れるため、年齢が上がるごとに妊娠のハードルも上がっていきます。このように自然妊娠は簡単にできるものではないため、夫婦で協力して妊娠しやすい環境を構築し、妊娠の確率を高めていくことが重要です。
近年の晩婚化を背景に妊活が広まった
「妊活」という言葉が広まったのは、近年の晩婚化によって不妊に悩む男女が増えたことが背景にあります。
日本人女性の平均初婚年齢や平均初産年齢は、昭和50年代から上昇傾向です。
参考:厚生労働省「令和3年度 出生に関する統計の概況」
令和元年の時点では平均初婚年齢が29.6歳、平均初産年齢が30.7歳と、昭和50年と比べるとどちらも約5歳上昇しています。
女性の妊娠力は20代でピークを迎え、30歳以降は徐々に低下するのが一般的です。
晩婚化によって30代以降に結婚・出産が珍しくなくなった現代では、昔と比べると自然妊娠に至らないケースが多くあります。
そのため、妊活の重要性が世間で広く知られるようになりました。
 妊活では具体的に何をする?まずやるべきこと4つ
妊活では具体的に何をする?まずやるべきこと4つ
妊活を始めようと思っても、具体的に何をすべきかわからない方も少なくありません。
夫婦で妊活に取り組もうと決めたら、まず下記のことから始めましょう。
● 夫婦で妊活について話し合う
● ブライダルチェックを受ける
● 妊娠しやすい体づくりをする
● セルフでのタイミング法をおこなう
ここからは、上記のやるべきことをそれぞれ詳しく解説します。
夫婦で妊活について話し合う
妊活は夫婦2人でおこなうものであるため、まずは夫婦で足並みを揃えるためにも、妊活に向けてしっかりと話し合いをしましょう。
夫婦で妊活の方向性や将来のプランに大きくズレが生じると、途中で温度差を感じて妊活にストレスを感じたり、夫婦関係が悪化してしまったりしてしまう恐れがあります。
<話し合いで確認しておくべきポイント>
● 子供はいつ頃欲しいのか
● 子供は何人欲しいのか
● 妊活にどれくらい費用や時間をかけられるか
● 不妊だった場合は治療をどれくらい続けるか
● 妊娠中や出産後の仕事はどうするか
夫婦で話し合ってしっかりと妊活の方向性や将来のプランを決めることで、結束力や責任感が生まれ、妊活もスムーズに進みやすくなるでしょう。
ブライダルチェックを受ける
ブライダルチェックとは、結婚や妊娠を控えている女性を対象とした検診メニューのことです。
ブライダルチェックを受けることで、妊娠・出産に影響を与える病気を持っていないか、赤ちゃんに感染する病気を持っていないかを把握できます。具体的には、下記のような検査をおこないます。
● 医師による問診
● 血液検査
● 内診・超音波検査
● 女性ホルモン分泌検査
● 感染症検査
● 甲状腺検査
● クラミジア抗体検査
● 子宮がん、乳がん検査
ブライダルチェックは、婦人科や泌尿器科、内科、不妊症外来などで受けられます。料金の相場は1~3万円程度で、原則として全額自己負担です。
ただし、ブライダルチェックを受けるには病院で受診する必要があるため、仕事が忙しく受けにいくのが難しいケースも多くあります。
その際は、会社の福利厚生にブライダルチェックを受けたり受けに行くための休暇を取ったりできる制度がないか確認してみましょう。
実際に、会社の福利厚生サービスとして馴染み深い「ベネフィットステーション」では、にしたんARTクリニックと提携した「AMH(卵巣予備能)の無料検査」を受けられるようになりました。
ブライダルチェックは男性も受けるのがおすすめ
ブライダルチェックは主に女性を対象とした検査ですが、クリニックによっては男性でも受診が可能です。
不妊の原因は女性にあると思われがちですが、実際には不妊の原因の約半数が男性にあることがわかっているため、ブライダルチェックは夫婦で一緒に受けるのがおすすめです。
男性のブライダルチェックでは、主に下記のような検査を受けます。
● 医師による問診
● 血液検査
● 精液検査
● 性感染症検査
● 尿検査
上記の検査を受ければ、自然妊娠が可能な精子か、人工授精や体外受精が必要かを把握できます。
妊娠しやすい体づくりをする
妊活に取り組むうえでは、妊娠しやすい健康的な体づくりが重要です。
食生活の乱れや睡眠不足、過度なストレスがかかっている状態が続くと、女性ホルモンのバランスが乱れてしまい、排卵にも影響を与えるため妊娠の妨げになります。
妊活中は栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動、ストレスを溜め込まずに発散するのを心掛け、妊娠しやすい体に近づけていきましょう。
セルフでのタイミング法をおこなう
タイミング法とは、排卵日に合わせて性交渉をおこない、妊娠の成立を目指す方法のことです。排卵日に合わせて性交渉をおこなえば、妊娠の確率が高まります。
排卵日はクリニックでの検査で予測するのが一番確実ですが、生理周期や基礎体温の記録を付ける方法や、排卵検査薬を使用する方法など自分で予測する方法もいくつかあります。
まずは自分で排卵日を予測し、排卵が行われるタイミングで性交渉をおこなうセルフタイミング法を実践してみましょう。
 妊娠しやすいタイミングは排卵日前の2日間
妊娠しやすいタイミングは排卵日前の2日間
妊娠がしやすいタイミングは排卵日の4日前から当日までの5日間で、なかでも排卵日の1~2日前は妊娠の確率がもっとも高い傾向です。
卵子は排卵してから24時間以内に受精しないと寿命を迎えてしまいますが、精子は卵管内で3日程度生き続けられます。
排卵が行われる数日前に性交渉をすれば、卵管内で精子が待機しているタイミングで排卵が行われ、精子と卵子が受精する可能性が高まります。
ただし、排卵日の6日以前や排卵日の翌日以降に性交渉をしても、妊娠する可能性はほぼゼロに近いので、妊娠を望むなら性交渉を持つタイミングに注意しましょう。
 妊活時に排卵日を把握する4つの方法
妊活時に排卵日を把握する4つの方法
妊活でまず把握しておきたいのが排卵日です。排卵日の直前を狙って性交渉を持つことで、妊娠の可能性を高められます。排卵日は以下の方法で自宅でも簡単に予測可能です。
● 生理日の記録を付ける
● 基礎体温の記録を付ける
● 排卵検査薬を使用する
● おりものの変化を観察する
ここからは、上記の方法をそれぞれ詳しく解説します。
生理日の記録を付ける
生理日の記録を付ければ、生理周期からおおよその排卵日を予測できます。生理周期とは、生理が始まった日から次の生理が始まる前日までの日数のことです。
生理周期がある程度一定していれば、排卵は次回の生理予定日の約14日前に起こります。生理周期は個人差がありますが、25~38日が正常な範囲です。
まずは数ヶ月間生理日の記録を付け、その平均値から自分のおおよその生理周期を割り出してみましょう。生理日の記録を付けるなら、スマホの専用アプリを使うのがおすすめです。
アプリで生理日を記録すれば、次回の生理予定日や排卵予定日を自動的に予測してくれます。
基礎体温の記録を付ける
基礎体温とは、起床直後の一番安静な状態で測定した体温のことで、女性ホルモンの分泌の影響で数値が上下します。
そのため、毎朝目が覚めて起き上がる前に婦人体温計で基礎体温を測定し、ノートやアプリで記録を付けておくことで排卵日を把握可能です。
正常な排卵が行われている健康な女性の場合、生理が始まると基礎体温が低下する「低温期」が2週間ほど続き、排卵が行われると、黄体ホルモンの影響によって基礎体温が約0.3~0.6℃上昇する「高温期」が2週間ほど続きます。
毎日基礎体温の記録を付けていれば、低温期から高温期に切り替わるタイミングがわかってくるため、排卵が起こるタイミングもある程度予測がつきます。
排卵検査薬を使用する
排卵検査薬とは、尿に含まれる黄体形成ホルモンの濃度によって排卵日を予測できる検査薬です。女性は排卵が起こる数日前から、排卵を促す黄体形成ホルモンの分泌量が増えます。
排卵検査薬を使えば正確に排卵日を予測できるため、排卵検査薬で陽性が出たタイミングで性交渉をおこなえば、妊娠の確率を高められます。
おりものの変化を観察する
排卵日は、おりものの量や状態の変化からある程度予測可能です。おりものも生理と同様に周期があり、生理周期や排卵日、体調などによって量や状態が変化します。
排卵日の2~3日前になると、生卵の白身のような透明で粘り気のあるおりものが大量に出るようになるのが特徴です。排卵日を過ぎるとおりものの量や粘り気が少なくなり、色も透明から白っぽい乳白色に変化します。
 妊活は男女ともに妊娠しやすい体づくりが基本
妊活は男女ともに妊娠しやすい体づくりが基本
妊活中は男女ともに日ごろから規則正しい健康的な生活を心掛けることが大切です。
妊活中は、以下のポイントを意識して生活を送るようにしましょう。
● 生活習慣を整える
● 葉酸を積極的に摂取する
● 食生活を整える
● 無理な食事制限をしない
● ストレスフリーで過ごす
● 適度に運動する
ここからは、上記のポイントをそれぞれ詳しく解説します。
生活習慣を整える
妊娠しやすい体づくりには、健康でいることが不可欠です。そのためにも、「1日3食栄養バランスのよい食事をとる」「適度な運動をする」「質のよい睡眠をとる」など日ごろから健康的な生活習慣を心掛けるようにしましょう。
特に妊活中の男女にとって重要なポイントは、質のよい睡眠をとることです。睡眠に深くかかわる「メラトニン」というホルモンは抗酸化作用が高く、ビタミンEの約2倍あります。卵巣を守ってくれる働きがあるため、妊活には欠かせないホルモンです。
メラトニンは22時ごろにの分泌が始まり、0~2時ごろにピークを迎える傾向です。良質な睡眠をとるためにも、22時を過ぎたらスマホやテレビを見るのをやめ、部屋の照明を暗くして眠りに入りやすい状態を作っておきましょう。
葉酸を積極的に摂取する
妊活中の女性は、葉酸を積極的に摂取するのが推奨されています。
葉酸は胎児の発育をサポートする重要な栄養素であり、積極的に摂取することで胎児の神経管閉鎖障害の発生リスクを低減することが報告されています。
ブロッコリーやほうれん草などの緑黄色野菜やいちご、マンゴー、納豆、ごま、海苔などに多く含まれているのが特徴です。
1日あたり食事からは240μg、サプリメントからも400μgを目安に葉酸を多く含む食品を積極的に摂取していきましょう。
出典:厚生労働省「2 対象特性 2─1 妊婦・授乳婦」
食生活を整える
妊娠しやすい健康的な体を作るためには、タンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素をバランスよく摂取するのが大切です。
外食やコンビニ食の多い食生活だったり、朝食を抜いたりしていると、体作りに必要な栄養素が不足してしまいます。
そのため、妊活中はできるだけ自炊の機会を増やし、1日3食の規則正しい食生活を心掛けるようにしましょう。
特に妊活中は、生殖機能や胎児の発育などをサポートしてくれる以下の栄養素を意識して摂取するのがおすすめです。
無理な食事制限をしない
妊活中は無理な食事制限を行わず、栄養バランスのとれた規則正しい食事を心掛けましょう。
無理な食事制限によって急激に体重が減少すると、脂肪細胞から分泌される「レプチン」という女性ホルモンの分泌量が減少し、卵胞刺激ホルモンや黄体形成ホルモンの分泌にも影響を与えます。
その結果、生理不順や無月経、排卵障害を引き起こし、妊娠しづらい体になってしまう可能性があります。妊娠を望むなら規則正しい食事をとり、適度な体重と体脂肪をキープするのが大切です。
ストレスフリーで過ごす
過剰なストレスは妊活に悪影響を与えるため、ストレスを溜め込まないように注意しましょう。
ストレスは妊娠に深くかかわる卵胞刺激ホルモンや黄体形成ホルモン、エストロゲンの分泌量が低下する原因になります。
女性ホルモンの分泌量が減ると、生理不順や無月経、排卵障害などが起こりやすくなるため、ストレスを溜め込んでしまうと妊娠の可能性が低下する可能性が高いです。
男性の場合も、ストレスが精子の量や質に悪影響を与える原因になります。仕事や妊活でストレスが溜まったら、熱中できる趣味に没頭してみたり、お風呂でリラックスしたりして気分をリフレッシュさせ、心身ともにストレスフリーな生活を心掛けましょう。
適度に運動する
BMIや体脂肪率が高いと、子宮や卵巣が内臓脂肪に圧迫されることで血流が悪くなり、卵巣機能が低下する可能性が高いです。
適度な運動習慣を取り入れ、適正なBMIや体脂肪率をキープすれば、卵巣機能が向上して妊娠につながりやすくなります。
ハーバード大学で行われた研究でも、「1週間の運動時間を1時間増やすごとに排卵障害のリスクが7%減少する」と報告されています。BMIが標準以上の場合は1日40分、1週間で合計5時間の運動が理想的です。
ただし、激しい運動で体重や体脂肪率が急激に落ちると、かえって妊娠力が低下してしまうため、妊活中はウォーキングやヨガなど体への負担が少ない運動を適度におこなうようにしましょう。
 妊活中の行為でのポイント
妊活中の行為でのポイント
妊活中に性交渉をする際には、下記のポイントを意識しておこないましょう。
● 回数を増やす
● 1~2日おきの頻度でおこなう
● 射精後気になるなら腰を高くする
ここからは、上記のポイントをそれぞれ詳しく解説します。
回数を増やす
性交渉の回数が増えれば、それだけ精子と卵子が出会いやすくなり、妊娠の可能性を高められます。ただし、妊娠の確率が高くなるのは一般的には週に3回までといわれています。
週4回以上回数を増やしても妊娠の確率に大きな差が出ることは少ないため、心身への負担も考慮すると週3~4回の頻度で性交渉をおこなうのがおすすめです。
1~2日おきにの頻度でおこなう
米国生殖医学会によると、「排卵日の4日前から排卵日の前日まで1~2日おきに性交渉すると、妊娠する確率が高くなる」と報告されています。
ただし、無理に性交渉の頻度を増やそうとすると、お互いにストレスとなって妊活に悪影響を与える恐れがあるので、無理のない範囲で実践してみましょう。
参考:日本産婦人科医会「9.タイミング」
射精後気になるなら腰を高くする
「射精後に腟内から精液ほとんどが流出して妊娠できるか不安」という方も多いですが、その心配は必要ありません。
基本的に精液は射精してから約30分で液状となり、一部は腟内から流れてしまうものの、元気な精子はすぐ子宮頚管に進入します。
通常、1回の射精で2~3億匹の精子が腟内に放出されますが、そのうち1匹が卵子の中に入れば妊娠が成立するため、精液がほとんど流出しても問題ありません。
ただ、それでも不安な場合は後背位や屈曲位のように深く挿入できる体位で射精してもらい、すぐ腰の下にまくらを入れて骨盤を高くしてしばらく安静にする方法もあります。
 妊娠中に気をつけたいこと
妊娠中に気をつけたいこと
妊娠の確率を高め、元気な赤ちゃんを出産するためにも、妊活中や妊娠中に下記の行動には注意が必要です。
● 体を冷やす
● 睡眠不足な生活
● 生ものを摂取する
● カフェインの摂り過ぎ
● トランス脂肪酸を含む食品を摂取する
● 喫煙や飲酒
なお、これらの行動を取らないよう気にし過ぎてしまうことがかえってストレスになってしまう場合もあります。
控えておくべきであることは押さえておきながらも、もし以下の行動を取ってしまった場合であっても自分を責め過ぎることはしない考えも大切です。
体を冷やす
妊活中や妊娠中は体を冷やさないよう、体を温かくして過ごすようにしましょう。冷えによって血行が悪くなると、卵巣に酸素や栄養が十分に行き渡らなくなり、卵巣の機能が低下してしまいます。
妊娠中は赤ちゃんで骨盤内が圧迫され、体が冷えやすい状態になっているため、普段から以下のような対策で冷えを防ぎましょう。
● ぬるま湯の湯船に半身浴で30分以上浸かる
● 体を温める食材や飲み物を摂取する(かぼちゃ、にんじん、生姜、ニンニクなど)
● 体を温めるグッズ(カイロや腹巻き、靴下など)を活用する
ただし、体を温めるためといっても、ほうじ茶や紅茶についてはカフェインの取り過ぎにつながってしまうことのないよう注意が必要です。
睡眠不足な生活
女性の場合、睡眠不足はホルモンの分泌が乱れ、排卵のサイクルに悪影響を与える原因になり、男性の場合は精子の量や質が低下する可能性があります。
睡眠時間が8時間の人と比べると、睡眠時間が6時間未満の人は妊娠に至る確率が0.62倍になるという調査結果も出ています。
妊娠の確率を高めるなら短くてもでも6時間以上、できれば7~8時間程度の睡眠時間を確保するのが理想的です。
生ものを摂取する
食中毒は、不妊のリスクを高めるといわれています。生の肉や魚介類、卵などには食中毒を起こす細菌やウイルスが付着している可能性があります。
生ものの摂取によって食中毒に感染すると、下痢や嘔吐で脱水症状になり、重篤な場合は流産や早産になってしまう場合もあるため摂取は控えるのがおすすめです。
また、生肉や生の魚介類に付着している寄生虫が胎児に感染すると、先天性感染症を引き起こす恐れがあります。
多くの細菌やウイルスは加熱によって死滅するため、妊活中や妊娠中はしっかりと加熱処理した食品を摂取するようにしましょう。
カフェインの摂り過ぎ
少量のカフェインには血流を促進させる作用がありますが、過剰に摂取すると自律神経やホルモンバランスの乱れ、血行不良や不眠などを引き起こします。そのため、妊活に悪影響を与える可能性が高いです。
実際に、厚生労働省もカフェインの過剰摂取は流産や出生児の低体重、将来的な健康リスクがあるとして注意を促しています。
妊活中や妊娠中はできるだけノンカフェインの飲み物を選び、カフェインの摂取量を控えるようにしましょう。
参考:厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~」
トランス脂肪酸を含む食品を摂取する
トランス脂肪酸の過剰摂取は、悪玉コレステロールの増加によって動脈硬化や心臓疾患などのリスクを高めることがわかっています。
また、排卵障害や子宮内膜症、精子濃度の低下など生殖機能にさまざまな悪影響を及ぼすリスクがあります。
トランス脂肪酸は、マーガリンやファットスプレッド、ショートニングなどの植物性油脂や、これらを原材料に使ったパンやケーキ、ドーナッツ、スナック菓子などに多く含まれている傾向です。
妊活中や妊娠中は上記食品の摂取をなるべく控え、バランスのよい食事を心掛けるようにしましょう。
喫煙や飲酒
妊活中や妊娠中は、喫煙や飲酒を控えるようにしましょう。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、血流の悪化を招きます。
その結果、卵巣機能の低下や精子の減少、勃起障害などが起こり、妊活に悪影響を与えます。お酒に含まれるアルコールも、男女の生殖機能の低下を招く原因になりやすいです。
また、タバコやお酒は本人だけでなく、お腹の赤ちゃんにも悪影響を与えます。妊娠の確率を高め、元気な赤ちゃんを出産するためにも、男女ともにタバコとお酒はすぐにやめましょう。
特に男性は会社での付き合いで喫煙や飲酒をする機会が多いため、周りからの理解を得る必要があります。
 妊活の成功率は1年間で60%
妊活の成功率は1年間で60%
健康に問題のない成人女性とパートナーがタイミング法を用いた場合、一般的には1回で約10~20%、半年で約50%、1年で約60%のカップルが妊活に成功するとされています。
ただし、妊活の成功率は男女の年齢や健康状態、生活習慣などさまざまな要因によって大きく変わります。
特に精子や卵子、子宮などの生殖機能に何らかの問題がある場合、タイミング法だけでは自然妊娠が難しいケースもあります。
出典:日本産婦人科医会「9.タイミング」
妊活しても妊娠しない場合は不妊治療に移行する
妊活を続けてもなかなか妊娠しない場合は、不妊治療への移行も検討してみてください。不妊治療に移行するタイミングは、妊活を始めてから約1年が目安です。
ただし、下記のケースに当てはまる場合は、できるだけ早く不妊治療を開始するのが望ましいです。
● 妊活を始めてから半年経過しても妊娠しない場合
● 40歳以上で妊娠を望む場合
● 夫婦双方またはどちらか一方に不妊の原因がある場合
不妊治療は長期にわたる通院が必要であり、急な予定変更や体調不良で仕事を休まざるを得ない場合もあるため、職場での理解やサポートも重要になります。
もし、不妊治療を受けていることを職場に知られたくない場合や、今の職場で理解やサポートが得られない場合は、不妊治療のサポートが充実している会社への転職を検討してみましょう。
ただし、企業によっては「入社後〇ヶ月経っていないと育休が取れない」といった決まりがある場合もあるので注意が必要です。
不妊治療しても授からない確率は高い
不妊治療をしたからといって、必ず妊娠・出産できるとは限りません。下記の表は、厚生労働省が公開している年代別の出産率・流産率をまとめたものになります。
参考:日本産婦人科医会「2010年ARTデータ」
20代後半の女性が不妊治療をしても、出産まで至る確率は20%前後に留まります。30歳以降になると年齢を重ねるに連れて徐々に出産率が低下し、流産率の上昇が見られるようになります。
40歳以降になると不妊治療を受けても妊娠までに至るのは非常に難しく、妊娠できても流産してしまう可能性が高いです。
不妊治療は精神的にも金銭的にも負担が大きく、長期間治療しても子供を授かれない可能性が高いため、その点を十分に理解した上で治療を受けるかを検討する必要があります。
 不妊治療のサポートが充実している企業の特徴
不妊治療のサポートが充実している企業の特徴
厚生労働省では、令和4年4月に不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定する「くるみんプラス」など制度を新たに新設しました。
くるみんプラスに認定された企業では、不妊治療のための休暇制度や短時間勤務制度やフレックスタイム制、テレワークなど多様な働き方が設けられています。
社内でも不妊治療を受けている労働者に対して配慮するよう全従業員に周知されているため、不妊治療を受けながらでも安心して働けるのが魅力です。
なお、くるみんプラスに認定されている企業は、厚生労働省の公式ホームページで確認できます。
出典:厚生労働省「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」
 妊活について正しく理解し協力しながら妊娠を目指そう
妊活について正しく理解し協力しながら妊娠を目指そう
妊活は妊娠を望む男女が一緒に取り組まなければなりません。女性だけではなく、男性も妊娠について正しく理解し、お互いに手を取り合いながら妊活を進めていくことが大切です。
まずは夫婦で話し合って妊活の方向性を決め、妊娠しやすい体を作るために生活習慣や食生活を改善し、排卵日のタイミングで性交渉を持つことから始めてみましょう。
もし、妊活について悩みがある場合やなかなか妊娠に至らない場合は専門のクリニックに一度相談してみてください。
【監修】
阿部 一也
板橋中央総合病院 医長
東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。
現在は板橋中央総合病院勤務 専門は産婦人科。